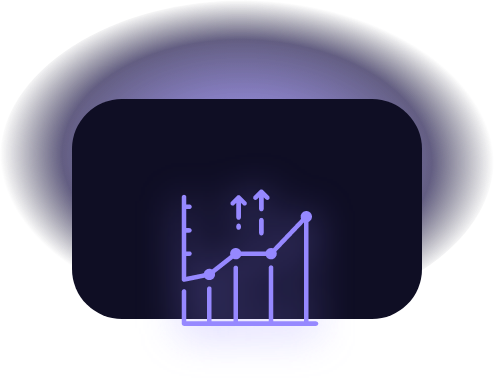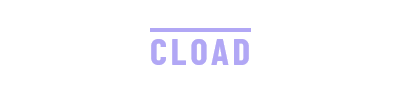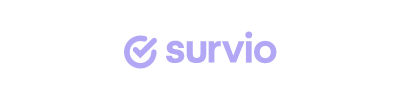「一摑一掌血一棒一條痕」の思想
陽明学の始祖である王陽明が立志について述べた言葉に、「一摑一掌血一棒一條痕」という言葉があります。安岡正篤先生はこの言葉を以下のように解しています。「人間は一つの問題を把握したり、経験したりする時には、ふらふらした気持ちでは駄目で、一度握ったら手形の血痕がつくくらいの、一本打ち込んだら生涯傷痕が残るくらいの、真剣で気合いのこもった、生命を懸けた取り組み方をしなければならない。」私は、人間の生き方というものは詰まるところ、このような姿勢で臨まねばならないものだと思います。ふらふらと刹那的な享楽を求めて、当てもなく彷徨することが人生ではないのであります。
「知行合一」の思想
世には博識ぶるばかりで何らの実践もない徒輩が多すぎるように思います。知識を有していても実践に至らねばその価値は乏しいものとなるというべきです。実践を想定し、実践と一体をなさぬ知識が如何なる価値を有しているというのでしょうか。私は、実践し得ぬ思想は本来的には思想とは言わないと強く断じます。
人は、考え方次第で如何様にでも変わり得るし、如何様にでも成れる。考えが志操に高められれば勇が生じ、勇が生じてくれば行が生まれてきて、そして業に繋がる。それ故、肝腎なのは考えを深めていくべく修養を重ねることであります。勇が生じないのは、修養が足らず志操の高まりが足らぬからです。志操が高ずれば自然実践へと発動されるものです。
王陽明は「一念発動処、便即是行了」、即ち、意識が一瞬でも発動したならばそれがそのまま実行したことなのであるとする「知行合一」論を説きます。朱子学では、「知(認識)」と「行(実践)」を明確に分離して、「知」を先、「行」を後と位置付け、価値的に「知」は軽く、「行」は重いとした。王陽明は、このような知行分割論、知行先後軽重論に反対し、人間はこの一瞬の今という分割不可能な時間に実在するのであって、この「現在」(現実存在)としての人間の存在態様を「知」と「行」に分割評価することは不可能であり無意味であるとする。そして、意識が発動して不善ならば、すぐさまその不善の意識を克服しなければならないと説く。これを私なりに先の文脈において表現すれば、発動した意識がそもそもその内実として善に届かない故、それがそのままの形で実行されたと評されるということになるでしょう。そもそも善に至らぬものとして我にその程度に現れるということに尽きます。勇なき振舞いとしてその程度のものとして表出されるということに断ぜられるのであります。「知」の深奥がその程度に浅薄皮相だということです。
「 VISION OF ACTIVE INNOVATION 」(復刻版)
~アクティブイノベーションという司法革命~
(2005年アクティブイノベーション設立の趣意に若干の加筆を施しました)
1.
第一に、「司法制度改革」の目的は、より身近でより利便性の高いリーガルサービスをあらゆる 国民の層に提供していく環境を整えることにあるはずであり、我々は「司法制度改革」の担い手として、その理念を具現化せんと発起した。我々は、唯一絶対の理念として、「徹底したクライアント第一主義」を掲げ、各施策においてこれを実践していく。
(1)真のワンストップ・リーガルサービスの実現
ご依頼の皆様の利便性を高めるべく、「真のワンストップ・リーガルサービス」を提供させていただく。ここで、「真のワンストップ・リーガルサービス」とは、第1に相談窓口を一本化することで、クライアントの皆様が各専門家のいずれかに相談されたらいいか迷われる事態を解消すること、第2に各分野の専門家を結集することでその生起する様々な問題に最も適切な解決策のご提示をなしうること、第3に各士業の専門分野に横断的な問題に対し統一的な解決策をご提示すること、第4に各士業に個別に依頼する場合に比し、クライアントの皆様の労力面、時間面、精神面、費用面のご負担を軽減すること、第5に各士業が同時に問題解決に当たることで迅速な処理が可能になること、これらのすべての要素を具現化したサービスを意味する。
このような「真のワンストップ・リーガルサービス」は、弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士・行政書士・土地家屋調査士等、各士業が同一の場所に所在し、一つの問題の解決に同時的にあたることによって初めて可能になると考えており、単なる複数分野の士業事務所が提携している状態とは決定的に異なるものである。いわばサービス内容自体を実質的に一体化していくことを志向する。
(2)全国展開の実現
我々はいわゆる「2割司法」を打破し、リーガルサービスの地域間格差を是正すべく全国展開を行っていく。
即ち、弁護士法人・司法書士法人等の士業法人の制度化は、「司法制革改革」の一環として都市部に集中した各資格者に支店展開により地方の需要に応える方策を与えたものである。しかるに現時点において(注・2000年代において)、かかる改革の意義を受けてこれを実践している法律事務所等の組織は存在しない。
我々は溢れる若さと情熱を武器に我々こそが「司法制度改革」の趣旨を具現化する担い手であると自覚し、地方の皆様のリーガルサービスに対する需要に応えていく。我々は「司法制度改革」の担い手・実践者として、「法の支配」の貫徹を目指す。
2.
第二に、我々は自らの人生をより意義深いものにしていくためにそのための努力を惜しまない。
(1)
我々はいわゆる士(サムライ)業という職業を選択した。その選択において、自らの力で自らの人生を切り開いていくことを自らに誓い、これを課した。
しかるに「司法制度改革」を受けた資格者大増員時代は、我々の受験時代に見えた司法業界の風景を一変させようとしている。
しかし、我々は士業を志した時の(ア)自己実現を果たしたい、(イ)社会正義の実現に寄与したい、(ウ)より有意な仕事を行いたいという人生の目標を簡単に捨て去ることはしない。
我々は市民のための司法の実現を目指す「司法制度改革」の理念に賛同し、これにより繰り広げられる事象、我々に課せられる課題をすべて受け入れる。その上で、我々として自身満足のいく職業人としての人生を送る地位を獲得することを目指す。それ故、現在固定化しつつあるいわゆる法律事務所等の二極化の現状をそのまま受け入れることはしない。かかる現状に果敢に切り込んでいく。
(2)
我々は独立の精神を持った若手士業集団である。
しかし、これが自己満足に陥ることのないように常に自己を戒める。そして、我々は他のメンバーに対し自身のプライドについて配慮を強いることはしない。自らに足りない点は、自身それと自覚しこれを真摯に受け止める勇気を持ち、その上で情熱を持って更なる努力を積み重ねていく。
我々の成すべきことはアクティブイノベーションという価値の実現であり、遇々努力の結果として自身がその地位にあることはあっても、その地位を守るために周囲が存在することはあり得ない。
我々はこれらのアクティブイノベーションのビジョンを実現する為に努力を惜しまない。この価値に些かでも疑問を生じ、また価値の実現に情熱を失うときはその者はアクティブイノベーションである意義を失うことになる。
以 上
Businessの世界からこの国の司法を変える
私は現在の境涯に至っても、「一摑一掌血一棒一條痕」の思想の下、ワンストップ・リーガルサービスというその理想とする究極の司法サービスの形態の実現を諦念してはいません。もとより私は自身実務家弁護士としてその体制を構築していくことのできる立場にはありませんし、もしかしたらそれ以上にこうしたことを社会に訴えかける資格すら喪失していると世人は言うかもしれません。
しかし、私は面壁6年余(達磨は面壁9年、私は6年です)の期間を通じたそうしたことの深慮の末、私にしか出来ないことがこの社会にはまだあると自覚するに至っています。是非、私の最後のそして畢生の仕事としてこの国のために働かせていただきたいと心より思います。本当の意味での人間の幸福というものは利他の精神が心を満たしたときに訪れるものであると私は獄の中で悟りました。
私は、これから不動産業をはじめとして種々の事業を行っていく所存です。法律的な問題を内含した事案は社会に数多存在するのであってビジネスの現場でそうした案件に遭遇することは決して珍しいことではありません。ビジネスの世界で社会における司法の役割を常に意識し理解していくことで、法的な問題を抽出していく機会は飛躍的に増大することは明白であると断言することができるのです。私は、元実務家弁護士として、社会のどこにそうした問題が潜在しているかよく知っています。今後、かかる案件を自ら事業化するのみならず、企業に対し新たなビジネスのスキームを構築していくことを提案していきます。
弁護士をはじめとする法律系士業に対しては、伝統的な事後的問題解決の業務に止まらず、企業の営業にプラスと働くような積極的な役割を担う関りを求めたいと思います。企業の営業活動に伴走し帯同する弁護士サービスの在り方を模索して参りたいと考えているのです。この点、その議論の場として、近々において、企業人と法律家による「ニュー法務ビジネス研究会」を立ち上げていく予定です。
上記のようなニュー法務サービスを提供するためには、当然ながら弁護士の意識改革とスキルアップが必要になります。それ故に今般、私は「若手弁護士に対する徹底して結果にこだわる実践的経営コンサルティングサービス」を提供していくことを企図したものです。そして同時に、寺子屋式の弁護士塾「志魂塾」を開講いたします。要するに、士業の皆さんに徹底的に自身の意識の向上とスキルの錬磨を図っていただくためのお手伝いをさせていただくと共に、自らの事業活動による法律問題の抽出の他、企業の協力の下において新たな企業活動帯同型の法務サービスの在り方を構築していくことで、不断に若手法律家のための仕事を創出していく仕組みを作っていこうと考えているわけであります。
どうですか、時代を担う志ある若手の弁護士や士業の皆さん。私と共に新たな司法サービスとビジネスのかたちを創設していく作業に力を尽くしていきませんか。一言でコンサルティングと言う際の世間一般のそれとは異なり、その内容は広汎で実際的であることがご理解いただけたと思います。結果にこだわるという文句はまさにそのような協働による仕事創出を含意したものであるのです。
その先に志を同じくする方々と出会い、私の理想とする真の「究極のワンストップ・リーガルサービス」の実現を眼にすることができたなら、私は本懐を遂げる幸甚なる思いで心を満たし世の役割を終えることとなるでしょう。
「幽囚の心得」
(元弁護士菅谷公彦の「獄中記」)
~第一章 真の「反省」とは如何なるものか~
私は真の「反省」というものは「自己肯定」に至る過程にあると考えています。
しかし、大衆社会がその人間が反省したと外形的に判断するに最も容易な様は「自己否定」の表現形態であるに違いありません。官憲が身柄の拘束にあたって強制力を用いて被疑者を代用監獄という閉鎖空間に留置することは、その被留置者に対し「自己否定」を促す単純な装置を作動させるようなものです。
では、この「自己否定」をした者にとって人生というものは如何に主観的に位置付けられていくものでしょうか。そして、その心理はどのようなものとなるのでありましょうか。「自己否定」の原因となった自身の行為を悔恨し、その行為時より以前の自分に戻るために時間軸をその時点まで巻き戻したいと願望するのかもしれません。しかし、勿論そのようなことは叶わないのであるから、その者にとっては二度と同様の過ちを犯さないことを誓い、そうと実践して爾後の人生を過ごしたとしても、人生のある一定の期間の時間は実質的には意味を失われ、その爾後の人生もまたハンデを負ったままマイナスからスタートするということになるのでしょう。慎ましく生きよと社会から命ぜられ、社会の定めたモデルのその枠内で最後尾に並ばされて頭を垂れて生きていくのです。それはそれでそのような「自己否定」モデルで改善更生を図る過程もその者本人にとっては(報いであるので当然ではありますが)相当心痛を伴うものがあると思います。
尤も私は翻って考えるにそもそも人間というものは自己を完全に否定したままに生き長らえることができるのかという点に関してはかなり懐疑的であります。その意味では他者に「自己否定」を求めるということは、実質的にはその者に対して死を求めるに等しいものだとさえ私は思慮するのです。しかし、世人はそのようなことに思いを致すことなく意外と簡単に「自己否定」という名の恭順を求めるものです。
このような「自己否定」の過酷さと不可能性を無意識に感知することで、人は「自己肯定」に逃避したいという心持ちになりやすいものだと言えます。積極的に「自己肯定」をするとまではいかなくとも、当該問題とされているその対象に向き合い直視するということを拒む者は実際には多く存在します。これらの者をここでは「堕落した自己肯定」モデルに属する者と呼ぶことにします。「堕落した自己肯定」モデルに属する者は、自己の過ちの故に科せられた刑罰を単に自己に対する不利益な処分として捉えこれを嫌厭するのが常です。このような者にとっては科せられた罰は創造的な意味としては何らの意味も有さないので、これに要する時間は退屈なだけであります。本を読んだり他者と談ずることも、単に退屈な時間を埋めるためだけの暇潰しの作業であって自身の人生に何らの積極的な意義を齎しません。受刑者の中にはこのタイプに属する者が多いことは否定できないでしょう。
実際に同衆の受刑者たちを見ると、世人一般から求められる完全な「自己否定」などする気は端から毛頭ない中で損得勘定を働かせて「自己否定」の態を装い、自身の解放に資するようにそのように振舞う人間がほとんどであります。そして施設側も表面に問題が現れなければそれでよいかのようなおざなりの対応に終始しておるのです。このような醜悪で怠慢な予定調和の欺瞞が繰り広げられているのが矯正処遇の現場の実際であり、その環境故に「堕落した自己肯定」がいよいよ助長され蔓延する素地が生まれているという悪循環にあるとも言えるのであります。
真の「反省」は「自己肯定」の過程にあると私が言うところの「自己肯定」とは、勿論、「堕落した自己肯定」に見られるところの自己逃避的な意味でのものを指すのではありません。以下、私がそうあるべきと考える真の「反省」たるものの内容を詳論します。
まず「自己否定」モデル同様、私は私の過ちを正面からそれとして受け止め、そこから逃避することなどは絶対にしません。同時に一方で「自己否定」モデルと異なり、その過去の自己の行為を人生の時間の中で消し去るべき対象として観念し行為以前に時間軸を戻したいなどとは全く思念することはありません。誤解を懼れず言うならば、過ちを犯した自分自身をも愛することができるかどうかという思考から始めるのです。その上で過ちを犯した自分は向後の人生において、如何にその全てを抱えながらこの機を捉えた生き方をしていくことができるかということを熟考していきます。留置、拘禁されたこの状態を如何に生きた時間としていくか、そして如何に人生のストーリーの中で有意味的な位置付けを与えうるかを心底から考え抜くのです。私の言うところの「自己肯定」の思想は、このように人生に起った全ての出来事に有意味性を与えんとする点で「堕落した自己肯定」モデルとは決定的に異なる思想なのであります。
私は、この思想を敢えて「有意味的な自己肯定」モデルと呼ぶこととしますが、この「有意味的な自己肯定」の過程というものは、言うは易し行うは難しであり極めて厳しく過酷のものです。前提として当然ではありますが、自らの過ちと一生涯向き合い続け、自己擁護的にこれを想念から消し去ろうとする所為は一切働きません。その意味におけるある種の十字架は一生涯背負って生きていくのです。そこから逃避し生き長らえようなどという卑怯は働いてはなりません。そして自身の為すべきこととして、与えてしまった被害についてその填補を貫徹することが必須なのは勿論でありますがそれだけでは全く足らないということ、その認識が重要です。たとえ被害弁償を貫徹したとしても、被害を負わせてしまった方々のその人生において失われた時間とその与えてしまった精神的苦痛を元に復してなかったことにすることはもはや不可能なのです。これは遅延損害金や慰謝料的な金銭賠償を為したとしても(もとよりこれらの全賠償を行って初めて被害弁償を貫徹したというべきです)同様です。このことはおよそ困難なことなのではありますが、被害を負わせてしまった方々があのような私による非違であり不義な行為はあったけれどもあのようなことがあったから現在のこの状態となったなというような、却ってある意味で肯定的に捉えていただけるくらいの何か、そのような何かをまで自らの力で現出させ顕していくこと、およそ現実的でないとの指摘を受けるでしょうがそこまでの務めを貫徹することが私が為さねばならない責任の果たし方なのであります。
人生の全ての場面を有意味的に捉えなければならないという思想からは、自身に目を向けてもその過ちですらそれがあったからこのような結果が齎された、これを起因として自身の人生がより多くの意味合いを有するようになったと総括しうる状態にまで自らの魂を高めていかなければなりません。自らの過ちが社会に与えた迷惑を凝視するならば、その余の爾後の人生において、社会的に意義のある貢献をその過ちが存しなかった場合に比しても、より大きくより多くの意味合いを有する程度にまで成し遂げなければならないのです。
過去の自分と将来の自分とを一つの正義に適うところの道徳的価値で貫かれた人生のストーリーで繋ぐこと、これが「有意味的な自己肯定」モデルの実践において真の意味で再びに「自己肯定」が叶った到達の地とも言うべき境地なのです。その境地に至る狭隘なる道程にある修養の姿の中にこそ「反省」の真のかたちがあると私は考えています。
その実現は被害者の方々の人生のストーリーの再構築にも一面において寄与しうるところがあるのではないか、私はまたそのようにも思うのであります。
「幽囚の心得」・目次
(元弁護士菅谷公彦の「獄中記」)
1. 真の「反省」とは如何なるものか
~「有意味的な自己肯定」モデルの提言~
2. 「連続性」の意義
3. 「固有性」を強める
4. 「一摑一掌血一棒一條痕」の思想
5. 「非日常性」の中に身を置く
6. 「リスタート」による完璧主義の追求
7. リベラリズムの限界・その内在する問題
~「見捨てられた人間」は如何にして救われるか
~
8. 「悪人正機説」は受刑者を救うか
9. 「承認欲求」を排する
10. 大衆を忌避せよ
11.「葉隠」の精神
12. 規範の存立根拠
~合理の裏付けと慣習的価値~
13. 人権論
14. 自由論
15. 愛国心
16. 正義論
17. 責任論
18. 幸福論
~幸福は「利他の精神」の発現の先にある~
19. 死生観
20. 切腹の精神と作法(自殺論)
21. 刑事政策の意義と刑罰の正当化根拠
22. 死刑廃止論
23. 懐疑主義と不条理
24. アクティブイノベーションという人生
~人間の「覚悟」というもの~